理事会へ、世帯主の代理人として配偶者(妻)が出席すること。一般的にはごく当たり前に行われていることですが・・・。
注意が必要です。その是非はご自身で判断ください。
ちなみに、さっさと答えだけ申し上げますと、「配偶者が出席することもできますが、規約の定めが必要」という回答となります。これは標準管理規約には盛り込まれていない内容です。
ですから、多くのマンションでは配偶者の出席は認められない可能性が高いと思われます。ご注意を。
目次
注意! 総会の場合は別なので注意
このページでは、「理事会へ、役員の代理人として妻が出席すること」を書いています。総会への妻の代理出席についてはまた別の話です。
総会についてはこちらで紹介しています。
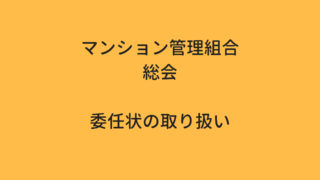
「区分所有者」は誰?
通常、管理組合の役員は、区分所有者の中から選ばれます。
さて、役員のことを考える前に少し聞いていただきたいことは、「区分所有者とは誰か?」」ということです。
法令上の区分所有者とは、区分所有法第2条第2項において、「区分所有権を有する者をいう。」と定義されています。区分所有権を有するもの、というのは、つまり部屋の持ち主のことで、登記の名義人のことと考えていただいて構いません。
夫、妻、2人の共有名義にしているケースが多いと思いますから、この場合、「区分所有者」とは、夫のことでもあり、妻のことでもあります。
役員は、区分所有者の中から選ばれる
部屋の所有者である区分所有者が、総会の決議によって役員として任命されるのが、管理組合の役員です。
夫が管理組合の総会で役員として指名された場合、夫が役員として、理事会に出席する必要があります。
仮に、夫ではなく妻の名前で管理組合の役員として指名された場合は、妻が理事会に出席することになります。
ここ、大事なので覚えておいてください。
総会で指名されるのは「個人」です。「世帯」として選ばれているわけではありません。
具体的にいうと、「101号室のご主人さん(●●さんという個人)を役員とすること」を総会で決定します。「101号室」が役員として選ばれたのではない、ということはよく理解なさってください。
マンション標準管理規約での規定は、特にない
標準管理規約において、理事会へ代理人の出席についての規定はありません。
ですから、マンションのルール的には、配偶者の代理出席については、認められるも認められないも、なにも決まっていません。
何も決まっていない場合、では何をもって決定するかというと、やはり民法でしょう。
民法的には、理事会への代理人の出席を「認めない」
役員として専任されるのは「個人」
まず最初に、「役員とは誰か?」という定義について。
覚えていますか?
個人が任命されたのであって、世帯が任命されたわけではなかったですよね。
「委任」なので、代理人はダメ
では、ご主人さんの代わりに奥さんが出席する場合、法的にどのような扱いになるのかな? というと、「理事(本人)の代理人を立てる」という考え方になります。
管理組合と、役員との関係は、「委任(ないしは準委任)の関係にある」と解するのが一般的です。委任の関係とは、強い信頼関係のもとに成り立つ契約であり、お任せする方の能力・資質を十分に吟味した上で成立するものです。
役員は総会で選出されますよね? 実際は、順番でみんなが当番することになっていたとしても、ルールの中では、区分所有者本人の能力・資質を考慮して選出されるものです。
ですから、
選ばれた本人以外(妻)が、代理人として理事会へ出席し、議決権を行使することは認められない、そう考えるのが妥当です。
法律的には配偶者であったとしても基本は他人ですから、無条件に代理として参加できる、というわけではないのです。
判例を見よう!
だいぶ前の判例ですが、本件についてはバッチリ最高裁で判決がでています。
区分建物の管理組合理事会への代理出席を認める規約が有効とされた最高裁判所判決(平成2年 11月 26 日)の概要について
(PDFが開きます)
http://www.mlit.go.jp/common/001119842.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/470/052470_hanrei.pdf
解説もつけておきます。
判例の要旨
- 管理組合規約を改正し、「理事に事故があり理事会に出席できないときは、その配偶者または一親等の親族に限り、これを代理出席されることができる」との規定を新設した。
- 法(※詳細は以下にて)が禁止した、法人の理事の行為の包括的な代理行為であるとして、区分所有者の総会決議の無効確認の訴えを提起した。
【結論】→法に違反しない。本規約は有効なものであると裁判所は判断した。
区分所有法49条とは?
上記で、※印をつけた場所は、原文では「建物の区分所有等に関する法律(以下「法」という。)49条7項により準用する民法55条」と記載されています。
引用して説明します。
区分所有法 第四十九条の三(理事の代理行為の委任)
理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
※民法55条も内容は同じ。ただし、民法55条は平成20年に削除済み。
「特定の行為の代理を他人に委任することができる」の言葉の意味は、「包括的に(つまり全部)任せちゃダメよ」、ってことです。
理事は信頼関係のもとに委任されてるのに、全部を他の誰かに丸投げしちゃったらその信頼は成り立たないでしょ? ってことが言いたい条文です。
そして、「理事に事故があり理事会に出席できないときは、その配偶者または一親等の親族に限り、これを代理出席されることができる」という条文は、読み方を変えれば、「その配偶者または一親等の親族に包括的に委任する」と取れますよね?
法と規約が矛盾します。
裁判では、ここが争われました。
で、結果として、裁判所は「違反しない」と結論づけました。
ということは、どういうことかというと。
- 上記条文があれば、配偶者は代理人として理事会への出席が可能
- ということは、この条文がなければ代理人の出席は認められない
と考えられます。
もちろん、条文は各マンションの実態に合わせてアレンジされればよろしいかと思います。
詳細は、管理会社なり、弁護士、マンション管理士などの専門家にご相談なさってください。
もし、理事会へ妻が代理人として出席していたらどうなるのか?
理事会への配偶者(妻や子)の代理出席は、実際には世の中の多くのマンションで行われていることですが、管理規約に照らし合わせると、それは認められないというケースが多いです。
代理出席を認める管理規約に変更しなければなりません。(すでにそうなっているようならなんの問題もありません)
仮に、管理規約に代理人を認める旨の記述がない場合、後々、裁判等になれば総会の決議そのものが無効とされる可能性があります。(判断には個別のケースによりますので、実際に裁判となってみなければわかりません)
リスクがあることは間違いありませんから、特に理由がないのであれば、ルールに沿った運営ができるよう、ルールの変更を検討するべきだと私は思います。
おまけ:管理会社フロントの実務的には??
ここまでが法令の話。規約に特別な文言がない限り、理事会へは、必ず区分所有者本人が出席しないといけません。
規約が改正されているか否かは、マンションによりけりでしょう。が、規約が改正されているマンションは、どちらかというと稀だと思います。(管理会社のスタンスにもよるでしょうが、標準的に対応している管理会社は少ないかとは思います)
もちろん、規約が改正されていない場合、本来は「妻の出席を認めないのが正しいやりかた」ですが、実務的にはそこまで細かく指摘するケースは、どうでしょう。少ないかなー、と思われます。よって、ご主人さんの代わりに奥さんが理事会に出席するのは、ごくごく一般的に行われています。しかしこれは運営としては明確に誤りです。
さて、これを、管理会社の従業員であるフロント個人がとやかく言う必要があるかどうかは、どうなのかなとは思うのです。
私個人の基準としては、会社の指示に従えば良いかな、と思っています。
会社がフロントへ特別に指示をだしていないようならスルーでいいかな、と。組合で問題視するようなら、そのときに規約改正を行えばよろしいかと。
最終的に、揉めた場合の尻拭いは会社にして貰えばよいでしょう。本質的に、お勤め先の管理会社の危機管理能力の話であって、フロントの采配で考える話ではないように思います。(組合より質問があれば別ですが)
絶対に、会社はこの実態を把握していますから。
ただし。ここでモメるようなら、理事会の決議の無効を指摘される可能性が高いです。ドミノ倒しで総会の開催そのものに瑕疵がある→決議が無効だ、というトラブルへ発展しかねない爆弾ではあります。
フロントが主体的に何かをしないといけないかどうかは、個人の感性と組合の雰囲気にもよりますが、一応、フロントの方は、原則論としてここに書いたことについては知っておくべきです。
よくある地雷の一つです、上手に回避して下さい。
大切なこと【追記】
管理規約に沿って総会運営がなされているか否かは、とても大切なことです。
なのですが、例えばルールとは違う運用がされていたとして、ではそれが直ちに間違いであり無効か、というと、それもちょっとどうなのかなーという気はします。
過去の決議状況や、明文化されていない住民の認識を総合的に勘案し、慎重かつ丁寧に判断しなければ、いろいろと見誤るかもしれません。
ルールとは、住人を縛るためのものではありません。よりよく住まうために、皆が尊重し、知恵を絞り、改良を加えてゆくもの・・・、だと思います。
法とルール、上手に付き合ってゆきたいものです。
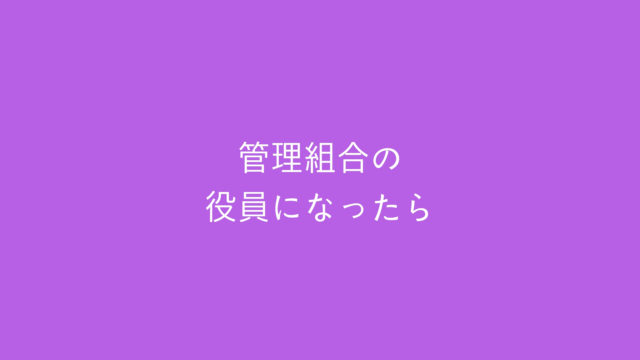

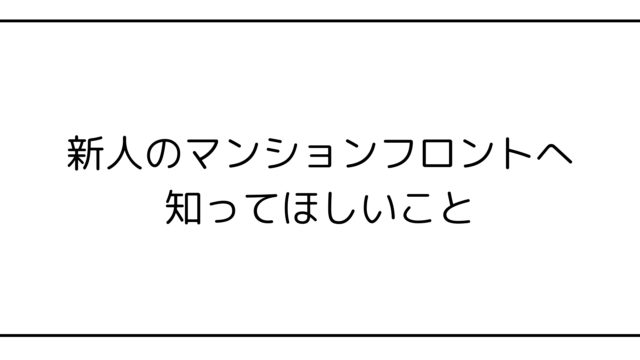
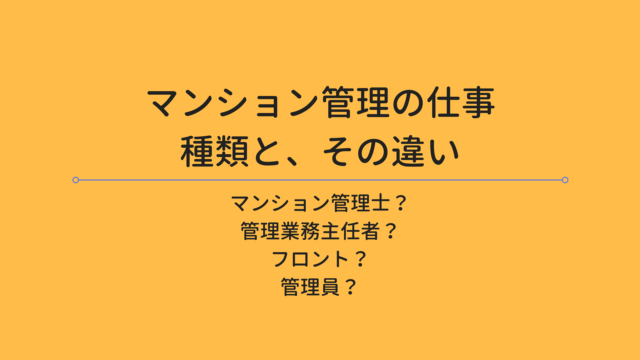
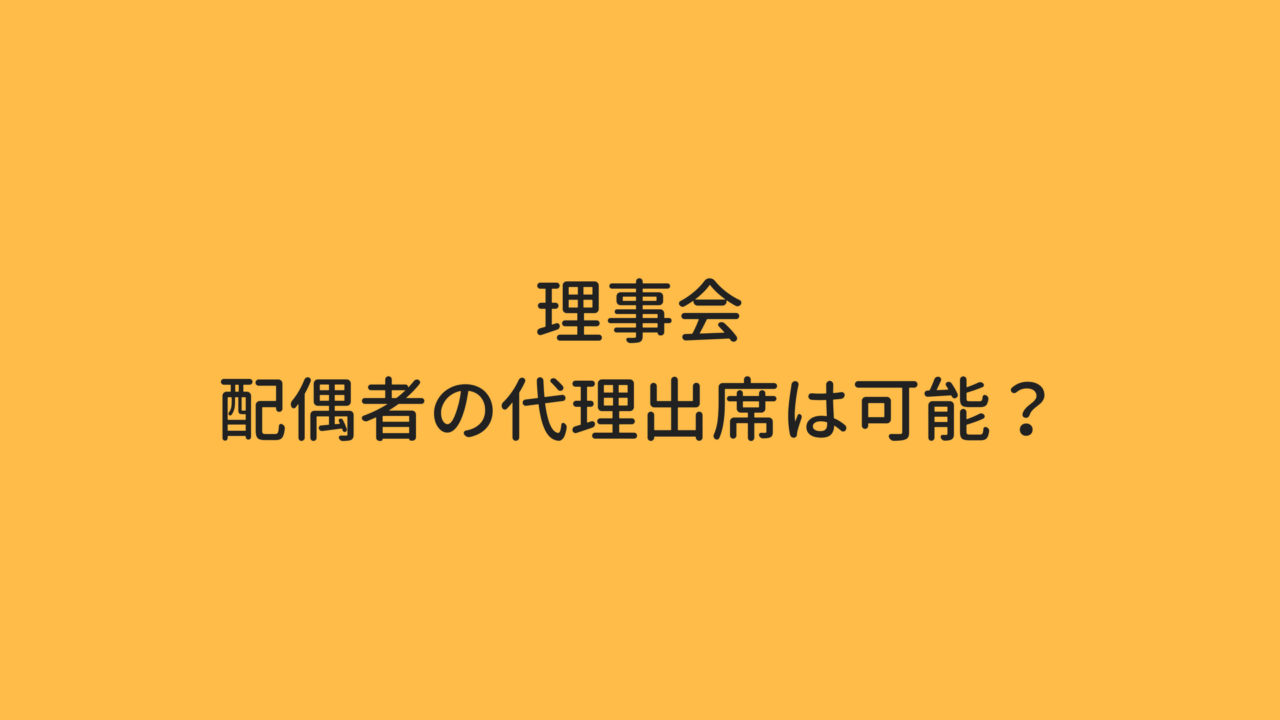

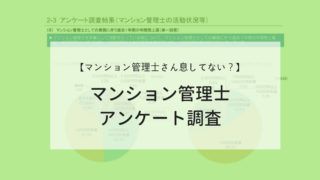

総会出席者は、区分所有者であろうが、配偶者であろうが、賃貸居住者であろうが、マンションを住みよくするために、マンションの現状を知っている方が最適です。 ここは法理論と実際が違う一番大きなところです。 そのためには、長時間マンションにいる方が最適なので、元気な高齢者が役に立ちます。 亀の甲より年の功です。
どうだろ。
法と違うというか、法は最低限度の決めごとしか示してくれませんから、自分たちのマンションの実情に合わせたルールを自分たちで決めていきましょうね、という感じかもです。
法では手の届かないところを決めていくのが管理規約なので~~。
また、古い話で恐縮ですが、50年前に入居したときは、公社分譲マンションだったため、共同住宅管理規約の名称で公社から提供された管理規約で運営していました。 ところが管理規約を盾に意見があり、その方の意見が正しいのですが、私も含め他の方は、おっしゃっている意味すら分かりませんでした。 「シロウト」はそんなものです。 分譲時の管理規約など、とても理解できません。 筋論と現実論との乖離です。
私のところでは、総会には委任の規定があり配偶者の代理出席が認められていますが、理事会には全く規定がありません。でも、総会と同じように組合員(区分所有者)の配偶者が出席しています。ずーっと続いている慣行なので、黙認していましたが、管理規約を改正するようにします。後で無効とされないように、理事会決議は配偶者理事を除いても過半数として総会に上程するようにします。何で今まで管理会社が黙っていたのか分かりません。いい加減なんですね。
最近は区分所有法、マンション管理の適正化の推進に関する法律等各種法令が後追いになる傾向があります。 民泊などが典型的な例で、管理規約で規制しても、実質的には規制できません。
古い張り紙で、みんながそれに従い、禁止されていることはしない時代は過ぎ、みんな勝手に過ごすことが風痛になっています。 自主管理していたころの方が、総会成立要件の確認は厳重で、出席者は実質的な区分所有者、賛成反対の票もきちんと数え、総会議事録にも記載していました。 欠席者はおろか小学校低学年でも足し算引き算ができれば可決したかどうかわかります。